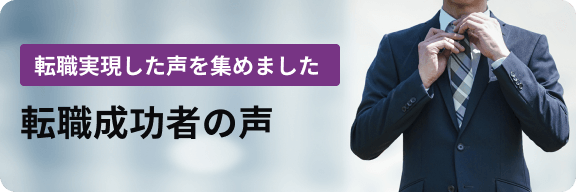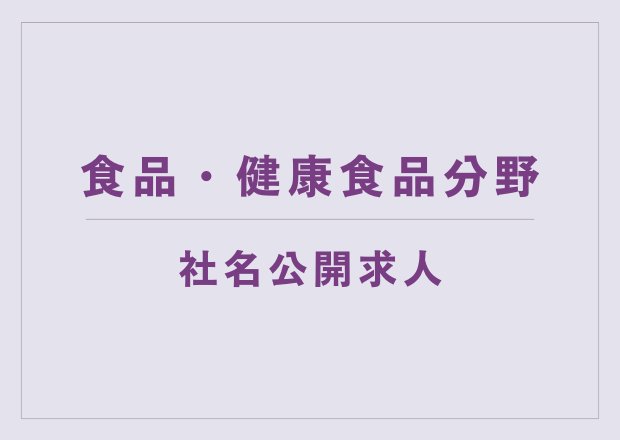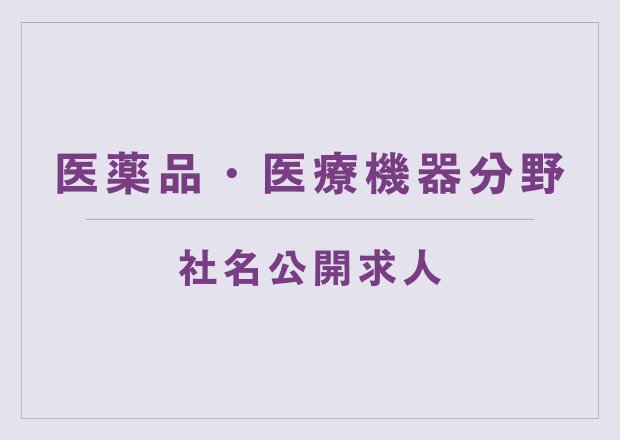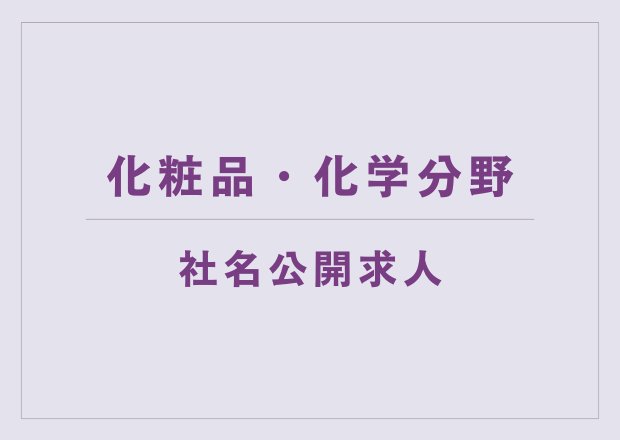食の未来を、自分の手でつくる。スタートアップで挑む植物性卵の開発。
- 2025/07/10
研究開発部 CTO
大場 國弘さん


プラントベース食品が注目を集める今、植物性卵製品を開発する食品スタートアップ・UMAMI UNITED JAPAN社。
同社のCTO(最高技術責任者)であり、共同創業者でもある大場様に、研究開発に懸ける想い、スタートアップで働く魅力、そしてこれから共に働く仲間へのメッセージを伺いました。
「植物性の卵」への挑戦。
その難しさこそが研究の面白さ。
──まず、大場さんのこれまでのご経歴について教えてください。
私は元々、小岩井乳業で乳製品の分析技術開発という、少しマニアックな分野に携わっていました。たとえば、「水の味がいつもと違う」といった違和感があったときに、その原因を突き止めるための分析方法を考えたり、適した分析機器を選定したりと、分析の基礎となる部分を担当していました。
その後、地元・香川の製麺機メーカー・大和製作所に転職し、「おいしい麺を作るための機械」を研究・開発する研究所の立ち上げに関わりました。麺の研究や開発、品質管理、工場ラインの見直し、マーケティング、メディア対応など幅広く経験し、食品製造の全体像を学ぶことができました。
──大場さんは会社の立ち上げから携わっていらっしゃいますが、UMAMI UNITED JAPANの立ち上げには、どのような経緯があったのでしょうか?

大和製作所に在籍中に、現在の共同創業者である山﨑と出会い、コンソーシアムとしてプラントベース食品の企画プロジェクトを共同で取り組みました。ただ、その時点では価格や市場戦略などの実現性までの検討には至らなかったので、いったん企画を見送りました。
その後、私は山﨑が勤めていたフードダイバーシティというメディア企業に入りました。当時の山﨑はプラントベース関連の書籍を出版したり、企業へのコンサルティングを手がけたり、プラントベースやハラールに関する情報をインフルエンサーとして発信・講演するなど、幅広く活動していました。
山﨑のやりたいことや考えに共感した私は、「食品メーカーでの一連の流れを理解している」という自身の経験を活かす形で、彼の構想を製品化するパートナーとして協業することになりました。
そして、フードダイバーシティ社で進めていたプロジェクトの中から、植物性卵の事業に特化した新たな挑戦として、山﨑とUMAMI UNITED JAPANを立ち上げました。
資金調達も自分たちでやりましたし、まったくゼロからのスタートでした。最初は海外のエンジェル投資家やアクセラレータープログラムからの支援で海外法人を設立し、その後、日本国内のベンチャーキャピタルや個人投資家の支援を受けて、日本法人を設立しました。現在の事業拠点は日本にあります。
──大場さんご自身も、元々プラントベースへの関心は深かったのでしょうか?
いいえ、実は最初から関心があったわけではありませんでした。
ただ、卵という誰もが日常的に使う食材を、植物性素材だけで再現する。──食品という幅広い分野において、あえて“手札を減らす”ような難易度の高いテーマに取り組むことが、研究者として非常に面白いと感じたんです。
卵を植物性素材だけで代替するというのは、使える手段がかなり限られています。
たとえば乳タンパクのような動物性の素材に頼れば、卵の食感や風味は比較的再現しやすい。しかしそれらをすべて除外した上で、いかに風味や機能性を実現するか。そのような、“制約の中でいかに突破口を見つけるか”という難易度の高さに、私は惹かれましたね。

──なるほど。限られた分野の食品を開発していくにあたって、「自らのこのスキルだったらやっていけるかもしれない」と感じた部分はありましたか?
ありましたね。やはりこれまでの幅広いキャリアが自信につながっています。
「研究はできるけどそれ以外は分からない」ではなく、全体像を見ながら開発を進める力が、今の仕事に活きていると思います。
日頃意識せずに食している「見えない卵」に着目。


──代替卵の開発にあたって、御社はどんな用途を想定して開発を進めているのでしょうか?
普段の食事のシーンでは、卵を「目に見える卵」として食べる場合と、「目に見えない卵」として食べる場合があります。例えば、オムライスやスクランブルエッグは「目に見える卵」、マフィンやパンケーキ、ハンバーグに使われているのは「目に見えない卵」というイメージです。どちらの「卵」の比率が高いかでいえば、後者の「目に見えない卵」です。
我々はその「見えない卵」の機能に着目し、各用途に特化した代替卵製品の開発を進めています。
──機能に着目した代替、そんなことができるんですね…!
最初に開発した「UMAMI EGG」は、卵が持つすべての機能をカバーできるように設計した、いわば万能型の“全卵の代替品”です。
しかし、実際にお客様とやり取りを重ねる中で見えてきたのは、卵に求められる機能が用途によって大きく異なるということでした。たとえば「風味を重視したい」という方もいれば、「つなぎとしての機能があれば十分」という方もいます。すべての機能を備えていることが、必ずしも求められているわけではないと気づきました。
そこで私たちは、味に特化した「UMAMI EGGフレーバー」や、つなぎ機能に特化した「UMAMIバインダー」など、派生製品を分化・展開することで、多様なニーズに応える開発へとシフトしています。
用途に応じて必要最小限の機能に絞った製品を開発することで、コスト面でも無駄のない、現場にフィットした提案が可能になりました。
“特別”ではなく“あたりまえ”としてテーブルに並ぶプラントベースを目指して

──プラントベース食品としての価値の提供についてはどのようにお考えですか。
プラントベースの食品って、どうしても「サステナブルだから」「ヴィーガン対応だから」という文脈で語られがちですが、私たちが目指したいのは、それよりももっと自然な形で受け入れられることです。
「なんとなく美味しそうだから手に取った」「いつも食べているこの商品、実は植物性食品だったんだ」
――ヴィーガン対応やサステナビリティというのを“売り”にするのではなく、気づいたら食卓に代替製品が自然に組み込まれている、そのような存在にしていきたい。
実際、そんな理想に近い商品づくりに取り組んでいる企業もあります。
たとえば、当社の製品をご使用いただいている、都内百貨店に出店するジェラートショップでは、乳や卵などの特定原材料を使わないジェラートを開発し、アレルギーを持つお子様もご家族と一緒に、味に我慢することなく楽しめるような商品づくりをされています。
ごく普通に売られているアイスが、実はプラントベース食品だった。そんな“特別に見えない特別”を、当たり前の選択肢として届けていきたいと考えています。
自由に考え、自由に挑む。
少数精鋭のUMAMI UNITED JAPANだからできること。

──大場さんご自身は、スタートアップでの仕事のどんなところに面白さを感じていますか?
スタートアップの面白さは、何よりも「自分の意思で自由に挑戦できる裁量の広さ」にあると思います。弊社では、日常的な開発や営業の場面では「これをやってみたい」と言ったときに、良い意味でそれを止める人はいません。大きな方向性はありますが、その手段は任されている。そんな自由度の高さがあります。もちろん、「〇〇がやりたいです。費用は300万円かかります!」なんて言われたら、ちょっと待てとストップをかけますけどね(笑)
──これまで培ってきた自分なりのスキルを発揮できる、ということですね。
そうですね。たとえば開発チームでは、「この方法でやってください」と指示するのではなく、メンバー自身が自由に手法を選んでゴールに向かっています。ただし完全な放任ではなく、あらかじめマイルストーンやゴールを設定したうえで、毎週のミーティングで成果や状況を共有し合い、「こういうアプローチもあるかもね」と意見を出しながら進めていく、そんなスタイルです。
営業でも同様で、各メンバーが持っている元々のネットワークや強みを活かして、自由度の高い動き方ができています。
「これをやってみたい」という意見には、「是非やってみよう」と背中を押す文化があります。
──逆に、スタートアップで大変なこともありますか?
もちろん大変なこともあります。やるべきことが多岐にわたるのは事実です。そこに面白さを感じられるかどうかで、スタートアップの向き不向きが決まってくるとも思います。
大企業や中小企業に勤めていると、「これをやってください」という指示を待ちながら業務を進めることも時にはあると思います。そんな環境にもどかしさを感じるような方にとっては、自分にプラスになる刺激が多いと思います。常に自分の意思で動き、自分で道をつくっていくような働き方を楽しめる方にとっては、最高の環境です。
──CTOである大場さんの、現在の業務内容を教えてください。
会社の運営はもちろん、商品のアイデア段階から上市に出るまでの全体の流れを把握し、自分自身で手を動かしながら進めています。
具体的には、原料調達、新素材や新商品の開発、既存商品の改良。それから在庫の把握や流通の部分まで、一連を把握しています。
──本当に一から全部見ているんですね。
それから、御社は現在工場設立を進めていると伺いましたが、立ち上げ業務にも関わられているのでしょうか。
はい、今まさに進めているところです。工場長候補やエンジニアリング会社、工場オーナーと連携しながら、機械の配置や製造プロセスの構築など、内部の設計にも深く関わっています。どんな機械をどこに置くか、このプロセスでどう製造を進めていくかなど、一つひとつを詰めている段階です。
──スタートアップとして組織構築の真っ最中だと思いますが、今現在のR&D部門の組織構成を教えてください。
R&D部門は現在、素材開発・商品開発・工場設営の3軸に分かれて動いています。
素材開発では、たとえば現在、豆原料を自社で加工し、新たな素材の開発をメンバー4名と取り組んでいます。商品開発は、素材同士を組み合わせて、お客様の求めるニーズに合う用途に特化した代替卵製品を開発しています。
お客様にとって実現可能な研究開発を。
──大場さんが研究や開発にかける想いについて、改めて伺えますかでしょうか。
私が開発で一番大事にしているのは、「実現可能なものを作る」という視点です。
たとえば、年に1kgしか取れないような希少な原料を使ったり、卵の10倍の価格になるような代替品を作っても、結局誰にも届かずに終わってしまう。だから私は、「ちゃんと売れる」「消費者までちゃんと届く」製品を作るというのが、開発の基本だと思っています。
──その実現性の中には、開発から流通、マーケティングまでの視点も含まれるんですね。
そうですね。我々はBtoBの事業だからこそ、最終的にそれがどんな商品になって、誰の手に届くのかまで見通せなければいけないと考えています。
価格を重視したいのか、機能を優先したいのか。そこまで含めて考えなければ、パズルのピースが噛み合わなくなってしまう。そのためには、調達の視点、製造工程、物流や流通、さらには価格帯やニーズの把握や最終的な販売の仕方まで、幅広く見る必要があります。
──開発担当者がそこまで関われるのは珍しいですよね。
そうかもしれません。大手企業ではどうしても分業になることが多いので。
弊社では開発者も商品の上流から下流まで一貫して関われる。試作して終わりではなく、食品開発の“全体像”を掴めるのは大きな特徴だと思います。
──皆さん入社当初からそのスキルを持っている方ばかりなのでしょうか?
いえ、必ずしもそういう方ばかりではありません。もちろん開発経験がある方に来ていただいてはいますが、実際の業務に携わりながら知識を蓄え、今では製品開発から価格調整、顧客ニーズへの対応まで、自ら判断できる力をつけています。そうした一連の経験は、次のキャリアにも必ず活きると思います。
全体の流れを見て「本当に成立するか」を考える。そのような視点を持った開発が、これからはより求められていくと思います。
まさに変革のとき。
──今後、R&D組織としての方向性はどのようにお考えですか?
今後は、開発フローの整備や体制構築を本格的に進めていきたいと考えています。
これまでは私自身の知見をベースにスピード重視で進めてきた部分もあります。たとえば、弊社製品「UMAMI EGG」は構想期間が約1年、実際に開発に着手してから完成まではわずか2〜3ヶ月でした。
スピード感は私たちの強みとも言える一方で、現段階では開発フローが属人的になっているという課題もあります。今後は量産に向けて、誰がやっても一定の品質で開発できる仕組みや、再現性とスピードを両立できる安定的な体制づくりをしていきたいです。
そのために、開発マネージャーとも連携しながら、一般的な商品開発フローの構築を本格的に進めています。
──今後メンバーに加わる方々にとっては、まさに変革期のチームに関われるタイミングですね。
そうですね、今のUMAMI UNITED JAPANはまさに変革期。これから開発のフローを構築して、工場もできて、量産の体制を整えていく。そんな大きな変化の最中にあります。
その変革期に関われるというのは、ある意味とても貴重な経験になると思っています。新しく入ってくれる方にも、そこを一緒に作っていくフェーズを楽しんでもらえたら嬉しいですね。
また、今は工場長候補にしても、R&Dマネージャーにしても、実務経験が豊富なベテラン層に加わってもらっています。もちろんそれを否定するわけではありませんが、今後はより年齢や性別問わず、さまざまな視点のさまざまな意見が飛び交う開発体制にしていきたいと思っています。
──最後に、この記事を見て下さっている求職者の方へのメッセージをお願いします。
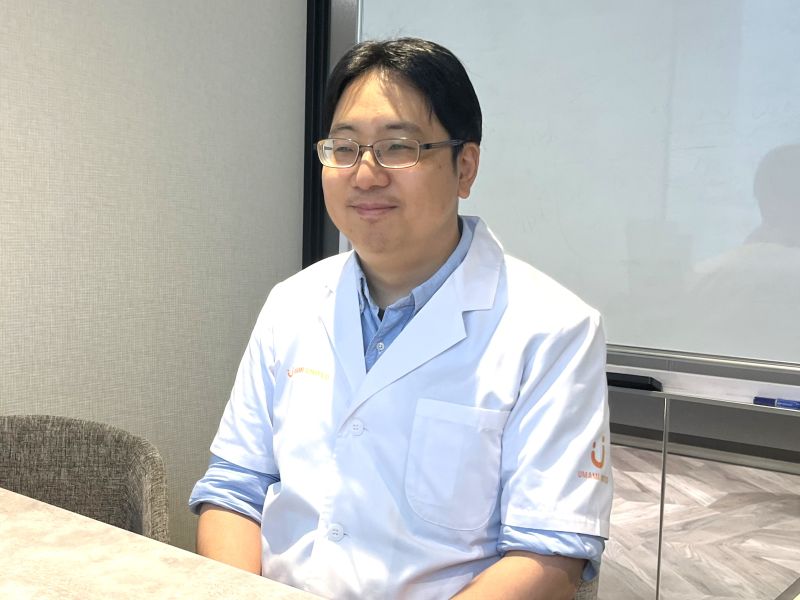
裁量を持って自ら考え、主体的に動ける方にとっては、やりがいを感じられる環境だと思います。ただし、そこには「考えることを放棄せず、責任を持って取り組む姿勢」も求められます。
基本的にはどんどん挑戦してほしい。方法に正解はありません。うまくいかなかったらまたみんなで話し合って、「じゃあこうしてみよう」と変えていけばいい。うまくいったら、「じゃあ、商品化に向けてどうしていくか」を個々の知見を共有しながら、そして何よりもチーム全体で楽しみながら進めていけるのが理想ですね。
やり方を自分で考えて動ける方、アイデアを自分の中に持っていて、それを形にするまで取り組んでいける方と、ぜひ一緒に働きたいと思っています。